スタートアップと聞くと壮大な社会課題の解決や、巨大市場でのシェア獲得といったストーリーを思い浮かべる人が多いかもしれない。しかし今回ご紹介する株式会社findは、誰もが一度は経験したことのある「落とし物」という、身近でかつ個人的な悩みから生まれた。
同社を率いるのはCEOの高島 彬氏。慶應義塾大学を卒業後、プロのバンドマンを目指し、その後金融大手のオリックスでキャリアを積んだという異色の経歴の持ち主だ。なぜ彼は落とし物という領域で事業を立ち上げる意思決定をしたのか。
その背景には自身の原体験から生まれた強い課題意識と、落とし物が返ってくる日本の文化をテクノロジーの力で世界に発信したい、という想いがあった。単なる業務効率化ツールに留まらないfindが目指す「おもてなし文化を価値にする」という志、そしてその志に共鳴する人々が集まる組織の強さの秘密に迫る。
【Profile】
株式会社find CEO・Founder:高島 彬氏
2013年オリックス株式会社入社。環境エネルギー分野、オープンイノベーション分野に従事。勤務中に共同創業者である代表取締役COOの和田龍氏と知り合い、共に起業することを約束。2021年12月に株式会社find創業。『落とし物クラウドfind』は鉄道をはじめとする各種交通機関、流通小売業を中心に現在全国33社に導入されている。
音楽から金融、そして起業へ。回り道してたどり着いた「人生を懸けるテーマ」

ーーまずは高島さんのユニークな経歴についてお聞かせください。起業に至るまで、どのようなキャリアを歩んでこられたのでしょうか?
高島:実は、大学を卒業してすぐに就職したわけではないんです。プロのミュージシャンを目指してバンド活動に明け暮れていました。パートはギターボーカルで、バンドリーダーとしてメンバーと機材車で全国をツアーして回るような本格的な活動でしたね。結局、24歳の時に東日本大震災を経験したことなどをきっかけに音楽の道は諦め、就職活動を始めることにしました。
職歴はありませんでしたが幸いにも新卒枠で応募することができ、ご縁があってオリックスに入社しました。当時からぼんやりと「いつかは起業したい」という思いがあったので、若くても中小企業の社長と対等に話ができる法人営業の仕事は非常に魅力的でした。
オリックスでは丸10年お世話になり、キャリアは前半と後半で大きく分かれています。前半は大手製造業などを対象とした、工場の設備投資に関するリースや融資など大規模な金融事業に携わっていました。一件あたり数十億円という金額を動かすダイナミックな仕事です。
ーーギターボーカルから一転、ビジネスの最前線に。大きな環境の変化に戸惑いはありませんでしたか?
高島:もともと新しいことを学ぶのが好きで、分からないことは素直に人に聞くタイプでした。変なプライドもなく、一から事業を学んでいくプロセスはむしろ楽しかったですね。目の前のことに一生懸命取り組むことで成果が出るのが面白く、充実した日々でした。
キャリアの後半にはスタートアップとの事業開発部門へ異動になったのですが、これが大きな転機でしたね。クラウドカメラの「セーフィー」という、その後にユニコーン上場を果たすスタートアップへの投資と事業提携を担当したのですが、CEOの佐渡島さんをはじめとする皆さんと一緒に働く中で、スタートアップという世界の面白さに完全に魅了されてしまいました。それまで手掛けていた数十億円という案件とは真逆の、1台数万円のカメラを売る仕事からのスタートでしたが、自分たちの手で新しい市場を創るんだという熱量とスピード感に大きな衝撃を受けたんです。

そこから「ベンチャーキャピタリストになるか、自分で起業するか」を真剣に考えるようになりました。ちょうどその頃、仕事を通じて出会ったのがのちにfindを共同で創業する和田(現・取締役COO)です。彼とは同い年で、仕事に対する価値観が驚くほど一致していたんです。「いつか一緒に面白いことをやろう」と話すようになりました。
ーー共同創業者の和田さんと出会い、すぐに起業のテーマは見つかったのでしょうか?
高島:いえ、それが全く見つからないんです(笑)。お互いに会社に所属しながら週末にオンラインで集まっては「どんなビジネスをやろうか」と話し合う日々が1年ほど続きました。しかしどれも「人生を懸けてまでやるテーマだろうか?」と、どこか腑に落ちない。悶々とした時期を過ごしていましたね。
潮目が変わったのは、私自身がプライベートでスマートフォンの入ったバッグを落としたことでした。スマホがないと何もできず、連絡を取るために公衆電話を探し回ったり、問い合わせ先の各所も非常に困惑していたり…。テクノロジーがこれだけ進化した現代で、なぜこんなにも非効率なことが起きているんだと愕然としました。
その時、この不便さがとてつもないビジネスチャンスに見えたんです。「これを解消するサービスこそ自分たちが探し求めていたテーマかもしれない」。起業というアンテナを張っていたおかげで、直感的に確信しました。すぐに和田にこのアイデアを話すと、彼もよく物をなくすタイプだったこともあり(笑)「それだ!AIとの相性も絶対に良い」と即座に意気投合。翌日には2人で集まってビジネスモデルを描き、findの挑戦がはじまりました。
ビジネスモデルの転換。鉄道現場で見た“おもてなし”が事業の核に

ーー「落とし物」というテーマは非常にユニークですが、どのようにビジネスモデルを構築していったのでしょうか?
高島:当初は落とし主と拾った人を直接マッチングさせる、いわば「落とし物版メルカリ」のようなサービスを考えていました。これで施設側は落とし物管理の業務から解放されますよ、という提案です。しかしこのモデルはうまくいきませんでした。
私たちの事業にとって最大の転機となったのが、京王電鉄さんのご協力で実現した「現場体験」です。駅の遺失物管理センターで実際に働かせていただき、落とし物がどのように扱われているのかを目の当たりにしました。そこで気づいたのは、拾われた物の約8割が近くにいる駅員さんなど、施設側のスタッフに届けられているという事実です。この商流を無視して、個人間マッチングだけで課題を解決しようとしていた自分たちの考えがいかに浅はかだったかを痛感しました。
さらに衝撃を受けたのは現場の方々の働きぶりです。忘れ物のお弁当箱を丁寧に洗ったり、汚れた体操服を洗濯したり…。センターには落とし物保管用の冷蔵庫や洗濯機が備え付けられていて、誰かの大切なものである落とし物を一つひとつ愛情を持って扱っている姿に胸を打たれました。それは決して会社の利益になる業務ではありません。それでも「お客様の大切なものをお返ししたい」という一心で、日々膨大な手間と時間をかけていたのです。
ーー現場での気づきが、現在の事業モデルに繋がっているのですね。
高島:まさしくその通りです。この日本人ならではのモラリティやおもてなし文化は、私たちが絶対に守り、発展させるべきものだと確信しました。そしてテクノロジーが介在すべきは、この文化をさらに発展、定着させるためにある。つまり手書きの台帳管理や電話での問い合わせ対応といった非効率な部分を解消し、現場の方々が本来のホスピタリティを発揮することに集中できる環境を作ることだと考えを改めました。

そこで、施設事業者様向けのサブスクリプションへと事業モデルをピボットしたのです。落とし物の写真を撮って登録するだけでAIが特徴を解析し、データベースを自動で構築。落とし主はWebサイトからチャットボット形式で問い合わせるだけで、AIが膨大なデータの中から自身の失くし物を探し出してくれます。
これにより事業者側は管理・捜索コストを大幅に削減でき、落とし主は24時間いつでもどこからでも問い合わせが可能になります。結果としてこれまで見つかりにくかったイヤホンや傘、手袋といった特徴の少ない物でも発見できるようになり、返還率が向上するという価値を提供しています。
ーー競合サービスも存在する中で、findが多くの企業に選ばれている理由は何だとお考えですか?
高島:私たちは単にシステムを売っているわけではないという点が最も大きな違いだと思います。私たちが営業先でお話しするのは機能や価格ではなく「落とし物が必ず見つかる世界を一緒に作りませんか?」というビジョンです。このビジョンを実現するためのパートナーになってください、そのためのツールとしてfindがあります、というスタンスなんです。
このアプローチがお客様に深く共感していただき、いまではお客様自身が「findが描く世界を広めたい」と、別のお客様を紹介してくださるという好循環が生まれています。現在、導入いただいている事業会社33社のうち、20社は京王電鉄さんかJR九州さんの現場を見学した上で導入を決めてくださいました。
私たちが営業するのではなく、ファンになってくださったお客様が次のファンを創ってくださっている。このパートナーシップこそが私たちの最大の強みであり、競合優位性だと考えています。
日本の“おもてなし”を価値に変える。findが目指す、次のスタートアップの形

ーー「落とし物」という課題解決の先に、findはどのような未来を描いているのでしょうか?
高島:いままさに、さまざまな可能性にチャレンジしているところです。直近では落とし物の中で法的に保管期限が過ぎ、企業に所有権が移ったものをメルカリさんの「メルカリshop」でリユースさせる循環モデルの実証実験を行っていました。拾った善意を未来につなぐ落とし物の循環モデルですね。これもお取引先企業の皆様がパートナーとしてfindのビジョンに共感してくださっているからこそできることではないかと思っています。
私たちが創業当初から自問自答してきたのは「日本人である私たちが、日本で起業する意味は何か?」ということです。シリコンバレーのビジネスモデルを真似るだけでは、本家には勝てない。では、私たちならではの価値とは何か。その答えが「落とし物が戻ってくる国」と言われる日本のおもてなし文化にあると考えました。
この世界に誇るべき文化を私たちのテクノロジーでさらに磨き上げ、世界中に発信していく。それがfindの存在意義であり、人生を懸けるに値するミッションだと確信しています。単なるマイナスをゼロに戻すだけでなく、忘れ物に込められた人の想いを繋ぎ、社会全体のコストを削減していく。これこそが私たちが社会に提供したい価値なのです。
このビジョンは国内の鉄道業界を越えてバス、空港、商業施設、スタジアムなど人が集まるあらゆる場所へと広がりはじめています。将来的には月額数万円で利用できる廉価版プランも提供し、町の映画館や銭湯といった小規模事業者にも導入を増やし、最終的には日本のあらゆる場所で落とし物が見つかるインフラを構築したいと考えています。

ーー事業のグローバル展開についてもお聞かせください。文化の異なる海外でも、findのサービスは受け入れられるでしょうか?
高島:自信はあります。落とし物が返ってきた時のうれしい気持ちは万国共通ですから。海外の方が日本で落とし物をして、それが無事に見つかったことに感動したという話をよく聞きますよね。このポジティブな体験を世界中で当たり前のものにしたいのです。
「海外ではどうせ見つからない」という諦めは、見つけるための仕組みがないから生まれるものです。私たちがその仕組みを提供し、物を返すことが経済的にも、そして人々の幸福度の観点からもプラスになるという成功事例をまずは日本で作っていく。
すでに国際線を運航するエアラインとの協議も始まっています。たとえば利用者数の多い東京ーハワイ路線から始め、ホノルルの空港や周辺の商業施設を繋いでいく。そうしたハブを世界各地に作ることで点と点が線になり、やがて面となって世界を覆っていく。日本の「おもてなし」をパッケージ化した、新しい形の価値輸出を実現できると信じています。
ーー日本のスタートアップのあり方そのものを変える挑戦かもしれませんね。
高島:そうありたいと思っています。これまで日本のIT業界はシリコンバレーの成功モデルをいかに早く、うまく日本市場に持ち込むかというゲームが主流でした。しかしそのやり方には限界があると思います。
『COTEN RADIO』で深井さんが話していたことなのですが、『これからの日本発スタートアップが世界で戦うための活路は、日本人ならではの「内発的なモラル」に立脚したビジネスを創ることにある』という言葉に深く共感しています。東日本大震災の時、誰に言われるでもなく多くの人がボランティアに駆けつけたように、日本人には見返りを求めず他者のために行動できる素晴らしい国民性がある、ということが例として語られていました。
私たちの事業はまさにその精神を体現するものです。AIという言葉を声高に叫ぶのではなくその根底にある「人の役に立ちたい」「困っている人を助けたい」という思いを価値に変えていく。私たちはその象徴的な存在となり、日本から世界へ、新しいスタートアップの潮流を生み出していきたいです。
“謙虚でいい人”が集う組織。事業と組織がシンクロする、findの成長エンジン

ーー壮大なビジョンを実現するためには、組織の力が不可欠です。findにはどのような方が集まっているのでしょうか?
高島:いわゆる「キラキラしたキャリア」を持つ人、例えば有名外資コンサル企業出身でマーケットバリューをあげていきたい、というようなタイプのメンバーは実は少ないですね。それよりも「愚直に課題解決をすることが好き」「誰かのために仕事をすることによろこびを感じる」といった心根の優しい、謙虚でいい人が自然と集まってきています。
これは私たちが採用においてスキルや経験以上に、ミッション・ビジョン・バリューへの共感を何よりも大切にしているからです。特に「findは、ミッション・ビジョン・バリューを実現するための集団である」という考え方が組織の根幹にあります。CEOである私を含め、誰か特定の個人に仕えるのではなく、メンバーひとり一人が会社の理念や価値観に向き合い、それに仕える。このカルチャーが役職や個人の能力にキャップされない、自律的な組織を創っていると感じます。
ーー人材採用のパートナーとしてProfessional Studioを迎えられていますが、どのような点を評価されていますか?
高島:Professional Studioさんは私たちの事業の表面的な部分だけでなく、その根底にある社会性や公共性といった、定性的な価値を深く理解してくださっています。その上で私たちの魅力やビジョンを、私たちと同じくらいの熱量と解像度で候補者の方に伝えてくれる。だから面接に来てくださる方はすでにある程度findへの理解が深く、本質的な議論からスタートできるんです。最初から最終面接をしているような感覚ですね。
また、単に経歴が華やかな「4番バッター」を集めるのではなく「findのカルチャーに本当にフィットするのはどんな人か」「他の会社では4番ではなかったかもしれないけれど、findで輝ける人は誰か」という視点で私たちのチームにとって最適な人材を提案してくれます。おかげで、事業と組織が理想的な形でシンクロしながら成長できている。本当に心強いパートナーです。

Professional Studio 市川:ありがとうございます。まずfindさんは事業の起点が“儲かる”や“市場が伸びている”ではなく、“みんなが困っているから”という公益性から興っていることが大きな魅力です。誰もが困ったことのある課題なので、多くの共感を呼び、応援者が集まりやすいんですよね。
顧客目線でも、隣接する交通機関や施設がfindを使うことで自社も便利になるため、顧客からの紹介によるネットワーク効果で、営業や広告費をかけずに顧客獲得が進むという、エンタープライズ向けのPLG(プロダクトレッドグロース)という他では見たことがない先進的なビジネスモデルだと感じています。
さらにはSaaS提供に加え、BPOも組み合わせることで顧客のオペレーションに深く入り込み、日々の運営に”なくてはならない存在”になっているため、素晴らしい継続率を実現しています。
その先には膨大な落とし物データを活用した二次流通や物流機能の受託など、大きな事業スケールが期待できますし、また、”落とし物”は世界共通の課題であるため、海外展開のポテンシャルも秘めている点も魅力ですね。
ーー採用支援する立場から見て、findさんの組織づくりはいかがですか?
Professional Studio 市川:組織面では理念共感を軸とした採用により、多様な人材が「一枚岩」となった結束力の強いチームを形成しています。MVV、事業戦略、組織に一貫性があり、着実な成長を遂げている点も素晴らしいと思います。当社としても、入社後の活躍まで想定した上で真にマッチングする人材を厳選してご紹介できるよう、これからも尽力していきます。
ーー最後に、今後の組織作りにおける課題と展望をお聞かせください。
高島:事業が急成長する中で、会社の成長スピードに個人の成長が追いついていくのは簡単ではありません。しかし、そのギャップを個人の責任にするのではなく「足りない部分はみんなで埋めていこう」というマインドセットを醸成することが何よりも重要だと考えています。
外部から経験豊富な人材を招き入れることももちろんですが、創業期から会社を支えてくれたメンバーが次のフェーズでまた新たな役割を見つけ、輝けるような環境を作りたい。0→1が得意な人もいれば、1→10や10→100が得意な人もいる。それぞれの強みを活かせる事業やフェーズを会社の中にいくつも用意することで、誰も置き去りにすることなく組織全体で3倍、4倍の成長を続けていける。「いい人」たちがやりがいをもって働き続けられる会社を創っていくことが、私の経営者としての大きなチャレンジです。
元バンドマンという異色の経歴を持つ高島氏がたどり着いた「落とし物」という身近な課題。それは、彼自身の原体験と日本の鉄道現場で目の当たりにした「おもてなしの心」が出会ったことで、国境を越える壮大なビジョンへと昇華した。
findの挑戦は、単なるSaaSビジネスの成功物語ではない。それは、日本人が古来から大切にしてきた「他者を思いやる心」という無形の価値を、テクノロジーによっていかにして現代のビジネスに転換し、世界に示すことができるかという社会実験でもある。
謙虚でいい人たちが集まり、同じビジョンに向かって突き進むfind。彼らが創り出す「落とし物が必ず見つかる世界」は私たちの社会をより温かく、信頼できるものへと変えていくに違いない。

最後まで読んで頂きありがとうございました。
『Startup Frontier』を運営するProfessional Studioは、スタートアップに特化したキャリア支援を行っています。エージェントはスタートアップ業界経験者のみ。キャリアや転職に関する相談をご希望される方は、以下よりお気軽にお問い合わせください。
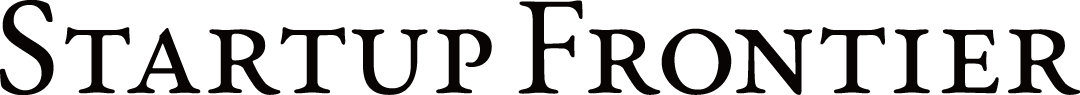

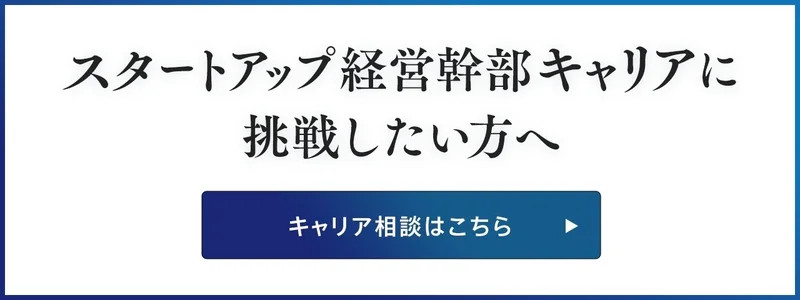 ≫無料相談はこちらから
≫無料相談はこちらから




