ヤフーの第二創業期を人事として支え、Supershipでは人事責任者、子会社の代表取締役として組織改革を断行。数々の輝かしいキャリアを経て、株式会社Hacobuの執行役員CHROに就任した吉田 毅氏。キャリアの後半戦にスタートアップというフィールドを選んだのはなぜか。
「人と組織を元気にする」をミッションに掲げる同氏のキャリアの軌跡、独自の組織論、そして大きな転機となった転職活動の裏側には、信頼できるパートナーの存在がありました。社会に大きなインパクトを与えるHacobuで「才能と情熱を解き放つ」挑戦を続ける吉田氏に、これまでの歩みと未来への展望を伺いました。
【Profile】
株式会社Hacobu 執行役員 CHRO
吉田 毅 氏
小売業、機器商社を経て、2003年にヤフー(現LINEヤフー)に入社。事業部門で営業企画業務に携わった後、2012年に経営体制刷新に伴い人事部門へ異動。組織開発室を新設し、1on1、リーダーシップ開発、診断型組織開発の展開など組織改革の主要施策を推進。2014年に企業内大学ヤフーアカデミアを開校後、ヤフーを退職。2015年にKDDIのインターネット旗艦事業会社、Supershipの立ち上げに人事責任者として参画。複数のスタートアップのM&AおよびPMIに人事として携わる。2019年からはグループ会社であるDATUM STUDIOの代表取締役に就任し、同社の業績回復を牽引。2022年に小売業DXに取り組む10Xに人事責任者として入社。
2024年5月よりHacobuに参画。
リアルビジネスからネット業界の雄へ。キャリアの原点と転機

――まずは吉田さんのこれまでのキャリアの歩みについてお聞かせください。キャリアのスタートは小売業界だったそうですね。
もともとは観光事業に興味があったのですが、ちょうど就職氷河期がはじまった時期でなかなかご縁がなく、当時海外へ積極出店していた大手小売スーパーに「流通業のソニーを目指す」というビジョンに惹かれて入社しました。1年ほど販売として従事していたのですが、私が退職して間もなくその会社は倒産の憂き目に。その頃、私は京都の実家に戻っていました。
――そこから専門商社へ転職されていますが、どのような経緯だったのでしょうか。
実家で過ごす中で、どこにも所属しないことの孤独感や怖さを痛感しまして。第二新卒枠で京都本社の専門商社に採用され、縁もゆかりもなかった東京で勤務することになりました。当時は友人もおらず、お金もなかったので、とにかく仕事に没頭する毎日でしたね。ただ、それが良かった。20代は仕事に夢中になることで、成果を出す面白さを覚えた時期でした。
私が扱っていたのは自動販売機などの省力化機器でしたが、コンビニの台頭で自販機業界が縮小していくのを肌で感じ、「業界全体が右肩上がりのフィールドで自分の力を試したい」と考えるようになりました。
――それが、次のヤフーへの転職につながるのですね。
ちょうど通信業界の規制緩和やインターネットの黎明期が重なり、通信・インターネット業界に大きな可能性を感じていました。
ただ、転職活動は難航しましたね。エージェントからも「吉田さんのキャリアならネットよりもう少し堅めのtoBが向いている」と言われてました。なかなか内定にたどり着かない日々を送ることになります。
そんな中、職場の先輩が「お前に合いそうな会社に付箋をつけといた」と渡してくれた求人情報誌の中にヤフーがあり、受けてみたらこれが幸運にも内定をいただくことができました。2003年、社員が500人くらいの頃で、ヤフーBBのモデムが普及し、ブロードバンドへ移行していく転換点でした。この時期のヤフーに入社できたことが、私のキャリアにおける最大のラッキーであり、最も大きな転換点だったと思っています。
――ヤフーでは、営業や企画職としてご活躍された後、人事へ異動されています。これはご自身の希望だったのでしょうか。
いえ、全くの想定外でした。営業や企画職として約9年間、数多くのチーム立ち上げなどを経験し、この道でキャリアを積んでいくものだと思っていました。しかし2012年、40歳の時に経営体制が大きく変わるタイミングで、新社長と新しい人事トップに呼ばれて「来月から人事な」と。
尊敬する先輩方からの抜擢は率直に嬉しかったですし、会社が大きく変わろうとする渦中にいられることにワクワクしました。一方で、全くの未経験である人事業務をやっていけるのかという不安も大きかったですね。
人事としての覚醒。組織開発と経営のリアル

――未経験から人事のキャリアをスタートされて、いかがでしたか。
人事部に異動してすぐ、当時の人事本部長から「組織開発室というのを作る。お前がやれ」と言われたんです。何をすべきか尋ねると「そういうことは自分で考えろ」と(笑)。そこでデスクに戻り、「組織開発とは」とネット検索するところから始めました。
当時は今ほど組織開発という概念が浸透しておらず、手探りの状態でした。書籍を読み漁り、専門家である大学教授が主催する泊まり込みの合宿に参加して体系的に学ぶなど、暗中模索の中で実践を重ねていきました。
――当時のヤフーには、どのような組織課題があったのでしょうか。
会社は連続増収増益を続けていましたが、組織内部は少しずつ硬直化が進んでいました。開発とビジネスサイドが受発注関係になって良いサービスが生まれにくくなったり、競合に優秀なエンジニアを引き抜かれたり。そうした中で経営陣は強い危機感を持っていました。私のミッションは、そうした組織の硬直化を解きほぐし、変革を推進することでした。
――3年間、組織開発に従事された後、KDDIグループのSupershipへ。これはどのような経緯だったのでしょう。
ヤフー時代の同僚で私より先に卒業していた友人がSupershipの立ち上げを担っていたんですね。彼から「人事の責任者として手伝ってほしい」と声をかけられたのがきっかけです。彼は私のことを信頼してくれて、何度も誘ってくれました。人にそこまで頼られる経験はなかったので素直に嬉しかったですね。ちょうど「ヤフーアカデミア」という企業内大学の立ち上げが一段落したという節目だったこともあり、新たな挑戦を決意しました。

――Supershipでは、ゼロからの人事組織立ち上げをご経験されています。
複数のスタートアップを統合し、さらに買収を繰り返しながら急スピードでスケールさせていく構想でした。そのため、各社に存在する人事制度やカルチャーをどう融合させていくか、自律と統制のバランスをどう取るか、非常に難しかったですね。教科書のない中で多くのハレーションも経験しましたが、仲間にも恵まれ、非常に良いチームで人事の基盤を築くことができました。
――その後、子会社であるDATUM STUDIOの代表取締役に就任されます。人事から経営トップへの転身ですね。
これもまた突然お鉢が回ってきた形です。前述の社長から「では営業経験もあるし、吉田さんで」と。営業経験と言ってもずっと昔の話ですし、何より当時の同社は組織が疲弊している状態でした。前年度の離職率も非常に高く、事業のトップラインが大きく減少する危機的な状況です。
しかし私は自分にお鉢が回ってくる時は、何かしら打ち返せるものがあるはずだと信じています。そこで「わかりました」とお受けし、2週間後には着任していました。
――どのように組織を立て直されたのでしょうか。
まずは離職に歯止めをかけ、採用を強化すること。これはまさしく人事の領域でした。幸いにも早期に優秀なビジネス責任者を採用できたことが非常に大きく、彼が事業を立て直してくれている間に組織の再建に集中することができました。この経験を通じて経営課題と組織課題が表裏一体であること、そして人事という機能が経営において非常にパワフルな「使える道具」であることを実感しました。
50歳の転機と「3つの軸」。信頼できるパートナーとの出会い

――DATUM STUDIOの代表を3年間務められた後、10Xに人事責任者として参画されます。これはどのような考えからの選択だったのでしょうか。
DATUM STUDIOの代表を退任するタイミングがちょうど50歳で、キャリアの後半戦をどう過ごすか深く考えました。そしてスタートアップで再び人事責任者として事業成長に貢献したいという思いに至りました。
その中で転職活動の軸として定めたのが、「インパクト・信頼・手触り感」という3つのキーワードです。社会の課題を解決する大きな「インパクト」が出せること。経営陣から強く「信頼」され、人事を実践できること。そして、組織の息吹を感じられる100〜300人規模の「手触り感」のある組織であること。この3つを満たす場所を探し、10Xにジョインしました。
――10Xでは理想の人事を実践される一方で、組織縮小というハードシングスもご経験されたそうですね。
事業環境の変化により、リストラクチャリングを断行せざるを得ませんでした。もちろんやりたくてやる仕事ではありません。しかし経営チームと共にこの難局を乗り越えた経験は私にとって非常に大きな学びとなりました。10Xで過ごした1年半は期間こそ短いですが、人事パーソンとしての器を広げてくれた誇るべきキャリアの一部です。
――そして、今回のHacobuへの転職活動が始まります。ここでProfessional Studioの市川代表と出会われたわけですね。他のエージェントとの違いはありましたか?
市川さんとの出会いは感動的でしたね。数多あるエージェントの中で本当にこちらの視点に立って企業を推薦してくださったのは市川さんだけでした。
まず私が伝えた転職の軸を元に、市川さん独自の観点を加えた評価項目を設定し、紹介企業を5段階で評価したリストをくださったんです。「ここは5なので絶対会ってください」「ここは3です」といったように、明確な理由と共に提示してくれました。
そして何よりレスポンスが驚くほど早い。その日に投げたボールは必ずその日のうちに返ってくる。一度も遅れたことがありません。そのスピード感と誠実さで、すぐに「この人と一緒に探していくのがベストだ」と確信しました。圧倒的な信頼感がありましたね。
Professional Studio 市川:ありがとうございます。吉田さんのご経歴を拝見した時「人事をレバーにして経営を伸ばした経験」を持つ、ほとんどお会いしたことのないタイプの方だと感じました。当時、HacobuさんではCFOの濱崎さんが「とにかく人事が課題だ」とずっとおっしゃっていて、経営陣の組織人事に対する本気度が非常に高かった。ここに吉田さんのような方が入れば、会社はものすごく飛躍するだろうという確信がありました。

Hacobuとの出会いとCHROとしての現在
――数ある企業の中から、最終的にHacobuへの入社を決められた理由は何だったのでしょうか。
一言で言えば「チームHacobuと馬が合いそうだ」と感じたからです。noteにも書きましたがもう少し解像度を上げると3つの理由があります。1つ目は物流という巨大な社会課題をテクノロジーで解決するというミッションへの強い共感。2つ目は代表の太郎さん(佐々木CEO)をはじめとする経営陣との対話を通じて、人事領域を心から信頼して任せてもらえるというイメージが持てたこと。そして3つ目はこれまでの経験を活かし、Hacobuの事業成長に貢献できると確信できたことです。
――代表の佐々木さんとの出会いが大きかったようですね。
初回のカジュアル面談から太郎さん(佐々木代表)が出てきてくれて、1時間があっという間に過ぎるほど意気投合しました。選考プロセスもユニークで、最終選考は経営会議でのプレゼンテーションだったんです。「吉田さんの人事観で、Hacobuをどういう組織にしていくか」というテーマで発表し、そこからまた1時間近く議論が盛り上がりました。
初回面談時、太郎さんは「金曜日の経営会議が一番楽しみなんだ」と語っていましたが、その言葉通り建設的な対話が飛び交う素晴らしい場で、ジョインする前にその雰囲気を体感できたのは非常に良かったですね。

――現在、執行役員CHROとして、どのような役割を担っていらっしゃるのでしょうか。
具体的には経営計画にリンクする人員体制計画、それに紐づく採用戦略、育成戦略策定です。加えて主要戦略のリード、ネクストリーダー育成も重要なミッション。また本部長としての役割は人事施策全体の円滑な遂行支援、人事チームの育成にあります。一方で経営メンバーとしては人事リスクの洗い出しおよび提言ですね。
いま一番注力していることの一つは私自身のテーマでもある「才能と情熱を解き放つ」をHacobuで実践していくことです。これはヤフーの変革期に掲げられていたスローガンで、私にとって非常に大切な言葉です。この御旗のもと、Hacobuの社員一人ひとりが輝ける組織を創り上げていきたい。その具体的な施策として現在は1on1の品質向上に1年がかりで取り組んでいます。
――Hacobuが抱える現在の課題とは何でしょうか。
第一はやはり採用です。事業が成長局面にある中で、その成長を牽引できる人材が全部門で必要です。もう一つはネクストリーダーの育成ですね。経営陣のリーダーシップに頼るフェーズから現場のオーナーシップによって事業が推進されるフェーズへと移行していく過渡期にあります。そのシフトをいかに実現していくかが、CHROとしての重要なミッションだと考えています。

ハイエンド人材と未来の組織。そしてキャリアビジョン
――吉田さんのようなハイエンド人材がスタートアップで活躍するためには、何が必要だとお考えですか。
3つあると考えています。1つ目は「仕事に対して夢中になれること」。スタートアップでは、役職に関係なく自ら手を動かす場面が多くあります。それを楽しめるかどうかは重要です。2つ目は「自らの知見を惜しみなく出し、チームに貢献できること」。そして3つ目は「アンラーンできること」です。
特に50歳を過ぎると、つい後進に道を譲る、教えるといったスタンスになりがちですよね。でもむしろ逆で、この年代こそ新しいことを貪欲に学ぶべきだと感じています。世代の違う若い友人から学ぶ、年上の先輩からも学ぶ。そうした柔らかさを持って、常に自分をアップデートし続ける姿勢が不可欠だと思います。
――ご自身の経験の中で、人事という仕事の本質をどのように捉えていらっしゃいますか。
組織の課題は事業課題の裏返しです。事業サイドは事業の課題を解きに行きますが、人事の役割はその裏側にある組織の課題を正しく見定め、優先順位にそって打ち手を講じることで、事業の成功確率を高めていくことにあると考えています。
またDATUM STUDIOの代表を経験して痛感したのは「経営者の多くは人と組織に困っている」という事実です。その一方で人事責任者は経営の本丸に入りきれないというジレンマも抱えている。「人事をうまく使えない経営」と「経営になりきれない人事」。この2つの狭間に立ち、両者をつなぐ架け橋となるモデルを作り出すことができれば、世の中に大きな価値を提供できるのではないかと考えています。
――最後に、今後のキャリアビジョンについてお聞かせください。
まずは、先ほどお話しした「才能と情熱を解き放つ」をHacobuで実践し、形にすることです。
また、長期的なテーマとして「AI時代の組織と人事」について型を見出すことに関心があります。たとえばゲノム解析が進み、候補者の将来の病気のリスクが分かってしまった時、人事はその情報をどう扱うべきか。テクノロジーの進化は私たちに新たな倫理観を問いかけます。そうした未来を見据えながら、人事という仕事が今後どうあるべきかを探求していきたい。残りのキャリアの中でその要点に触れ、新しい人事の型を見出すことができたら、こんなにワクワクすることはありません。
そして最終的には私のセルフミッションである「人と組織を元気にしたい」と願う人々やコミュニティをより広く支援していくことができたら、これ以上ない幸せですね。
リアルビジネスからキャリアをスタートし、インターネットの黎明期にヤフーへ。そこで運命的に出会った「人事」という仕事に導かれ、組織開発、スタートアップの立ち上げ、代表取締役としての組織再建と、常に人と組織の最前線で挑戦を続けてきた吉田氏。
その言葉の端々から感じられたのはキャリアを切り拓いてきた“人との縁”への感謝と、目の前の仕事に夢中になる誠実さ、そして「人と組織を元気にする」という揺るぎない信念でした。
50歳という節目を迎え、自らのキャリアの軸を問い直し、信頼できるパートナーと共に巡り会ったHacobuという新たな舞台。そこで吉田氏が実践する「才能と情熱を解き放つ」挑戦は日本の物流、ひいては社会全体を元気にする大きな一歩となるに違いありません。吉田氏の物語はキャリアの岐路に立つすべてのビジネスパーソンにとって、多くの示唆を与えてくれるものでした。

最後まで読んで頂きありがとうございました。
『Startup Frontier』を運営するProfessional Studioは、スタートアップに特化したキャリア支援を行っています。エージェントはスタートアップ業界経験者のみ。キャリアや転職に関する相談をご希望される方は、以下よりお気軽にお問い合わせください。
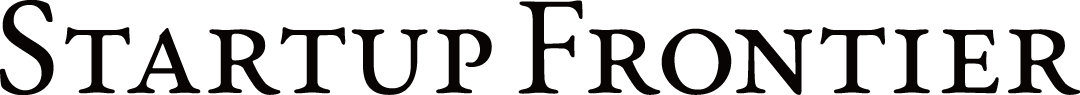
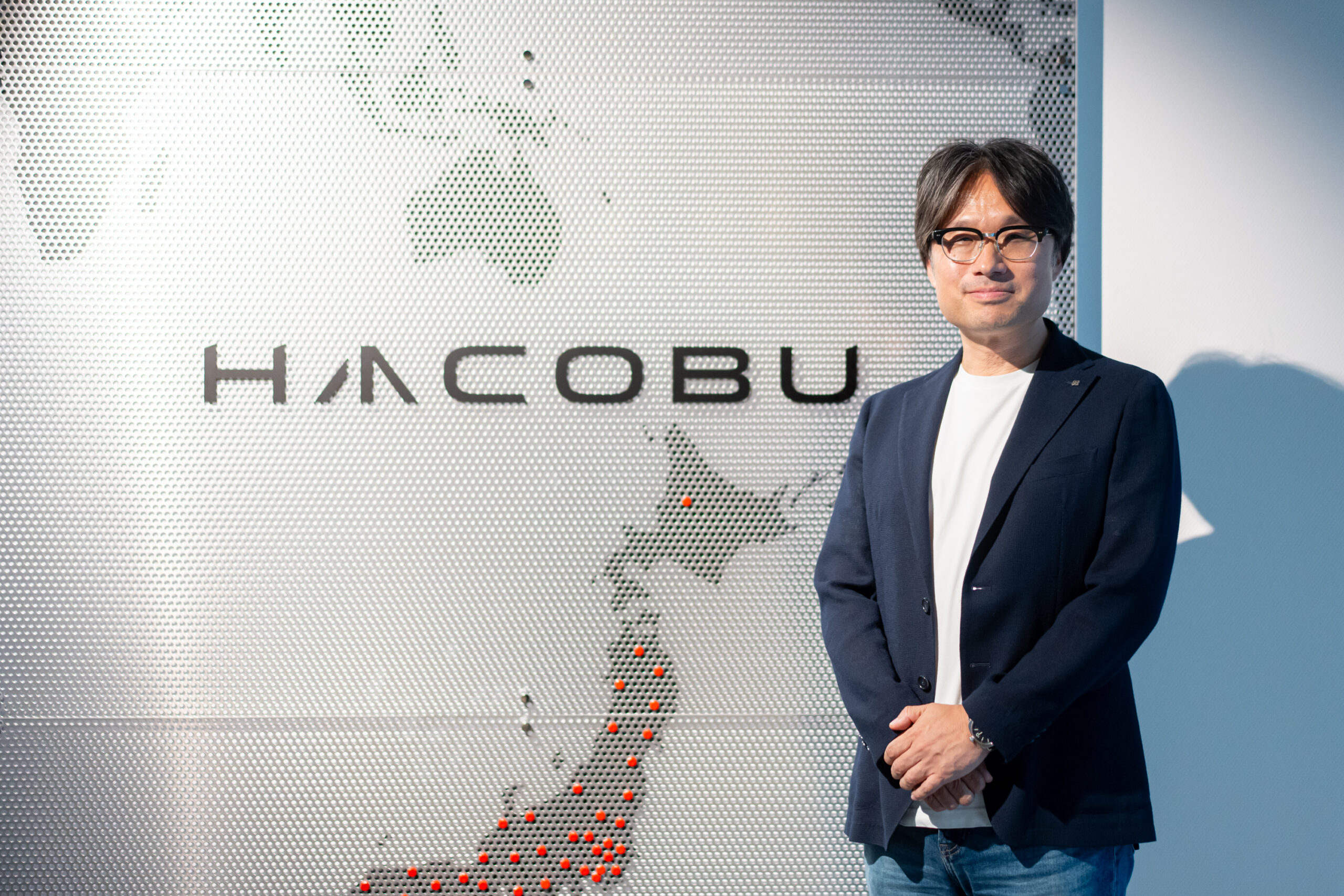
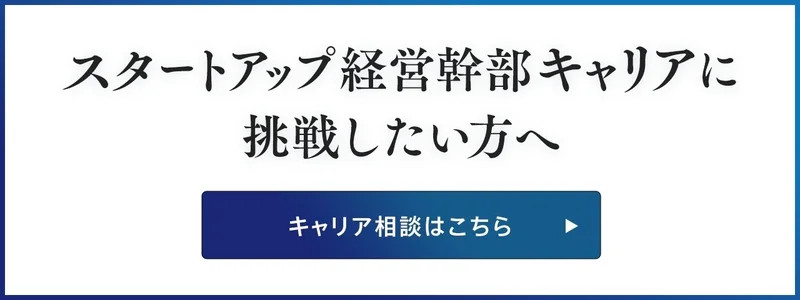 ≫無料相談はこちらから
≫無料相談はこちらから



