日本の労働人口が減少の一途をたどる中、特にIT分野におけるエンジニア不足は深刻な社会課題となっています。2030年には最大で約80万人が不足するとも言われる状況下で「挑戦するエンジニアのプラットフォームをつくる」というビジョンを掲げ、急成長を遂げているのがファインディ株式会社です。
同社を率いるのは、三菱重工業、ボストン コンサルティング グループ、そして創業期のレアジョブという異色の経歴を持つ山田裕一朗氏。なぜ彼はエンジニア支援の道を選んだのか。自身の原体験から語られる起業の軌跡、独自の事業戦略、そして組織づくりへの想いまで、その情熱の源泉に迫りました。
【Profile】
ファインディ株式会社 代表取締役:山田裕一朗氏
同志社大学経済学部卒業後、三菱重工業、ボストン コンサルティング グループを経て2010年、創業期のレアジョブ入社。レアジョブでは執行役員として人事、マーケティング、ブラジル事業、三井物産との資本業務提携等を担当。その後、ファインディ株式会社を創業。
挫折と挑戦が紡いだ、起業への軌跡

ーーまず、山田さんのキャリアの原点について教えてください。
私のキャリアの原点は新卒で入社した三菱重工業にあります。文系出身ながら、配属されたのは事業部の企画部門。上司も周りも技術系の方ばかりで、日々、設備投資の妥当性を精査するために技術者と膝詰めで議論を交わしました。そこで日本の「ものづくり」を支える人々の技術への情熱や深い知見に触れ、強いリスペクトの念を抱いたことが、いまの事業の根幹に流れています。
ーーなぜ、安定した大企業から戦略コンサルファーム、そして創業期のスタートアップへとチャレンジングなキャリアを選んだのでしょうか?
学生時代に日米学生会議の実行委員をやっていた仲間たちが、プロフェッショナルファームや外資系金融などでハードに働き、世界を舞台に活躍している姿に憧れていたんです。私自身、もっと厳しい環境で自分を成長させたいという想いが募り、ボストン コンサルティング グループへの転職を決意します。しかし、そこで最初の大きな挫折を経験しました。
ーー具体的にどのような挫折を経験されたのですか?
入社後の研修で出される問題に全く答えられず、ただ黙っていることしかできませんでした。日付が変わってもなお働く日々の中で「これは根本的に向いていない…」と痛感しましたね。まさに藁にもすがる思いでなんとか打開策を探していた時、インターネットで偶然「戦略コンサルを辞めて起業した」という方のブログを見つけ、強く共感したんです。いてもたってもいられず、直接連絡して会いにいきました。
ーーそして、創業期のレアジョブに飛び込まれたのですね。
はい。ブログの主がレアジョブ創業者だったのですが、彼の「スタートアップへの参加は早ければ早いほど楽しい」という言葉に「これだ!」と思ったんです。結局BCGには約1年で別れを告げ、給与額すら決まっていないまま当時まだ社員数10名ほどのレアジョブに7番目か8番目の社員としてジョインしました。
コンサルタントとしてお客様を支援するのではなく、自分たちのビジネスとしてユーザーの声に直接応え、改善していく。当事者意識を強く持って事業に向きあえる環境が、私の性に合っていました。

ーーレアジョブでの成功体験だけでなく、失敗談や困難だったこともお聞かせください。
自信満々でリリースしたスマートフォンでの英会話サービスが、端末が熱くなりすぎて使い物にならないなど技術的な壁にぶつかることもありました。また、会社が急成長する中で組織の歪みが生まれ、情報流出という大きな危機にも直面しました。
私自身も一度降格を経験し、たった一人のメンバーであるインターン生から「山田さんって昔からいる割に報われないですね」と言われたのも、いまだに忘れられない思い出です。グサッときましたが、それもまた事実だと。
ーーそのような濃密な経験を経て、起業を決意されるわけですが…。
そうした成功も失敗も含めた経験を通じて、それまで特別な人のものだと思っていた「起業」が自分にもできるかもしれない、というリアルな選択肢に変わっていきました。レアジョブで執行役員を務めながら、2014年には今のCTOとファインディの前身となる会社を設立し、本業と同時並行で活動を始めました。そして役員の任期満了をもってレアジョブを円満退社し、2016年に本格的にファインディを始動させたのです。
ーー創業後、最大のハードシングスはコロナ禍だったとうかがっています。
間違いなく最も大変な経験でした。ダイヤモンド・プリンセス号の報道があった時点でリスクを先読みし、新規採用停止などドラスティックな経営判断を下したのですが、その動きがあまりにも早すぎたことで社内に軋轢が生まれてしまって。同時に資金調達も困難を極め、多くの投資家が手を引きました。
社内の問題と資金調達という二つの課題に挟まれながら経営者としての至らなさを痛感するという、本当にヒリヒリする時期でした。結果的には2020年の4月に単月で過去最高売上を記録し、その実績を元に何とか資金調達を実施できましたが、この経験は経営者として私を大きく成長させてくれたと思っています。
事業の核心と、グローバルへの展望

ーー「つくる人がもっとかがやけば、世界はきっと豊かになる」という理念に込められた想いを教えてください。
日本の強みは海外の優れた技術を取り入れ、改善し、より良いものへと昇華させる「ものづくり」の力にあると信じています。その中心にいるのがエンジニアという「つくる人」たち。彼らがもっと事業の中心で活躍し、挑戦できるプラットフォームを作りたい、という想いがファインディの原点にあります。
ーー現在の主力事業について、それぞれが提供している価値を教えてください。
主に5つの事業を展開しています。IT/Webエンジニアの転職サービス「Findy」、ハイスキルなフリーランスエンジニア紹介サービス「Findy Freelance」、経営と開発現場をつなぐAI戦略支援SaaS「Findy Team+(チームプラス)」、開発ツールのレビューサイト「Findy Tools」、及びテックカンファレンスのプラットフォーム「Findy Conference」の5つです。これら人・組織・ツールという複数の事業を通じて、エンジニアの生産性最大化を多角的に支援しています。
ーー生成AIの登場は「過去9年分が3ヶ月で起きた」ほどの変化だったとのことですが、具体的に市場はどう変わったのでしょうか?
第一次のインターネット革命が「いかにモデムを売るか」みたいなステージだったとすると、第二次は2010年代のモバイル革命だったと思うんです。これはマーケタードリブンで、いかに小さな画面に最適化するかという、いわゆるUIUXといった言葉が中核の世界。今回の生成AIはまさに第三次といえる大きなパラダイムシフトといえるでしょう。なんといっても開発リソースが限界値まで下がって、いろんなプロダクトが作れる環境になりました。
ーー変化というより革命であると。
それぐらい「バイブコーディング」が一般化した数カ月だったかと思います。まさにエンジニアドリブンの革命だなと。この変化はエンジニアにとってこれまでの常識が通用しなくなるほどの大きな地殻変動です。働き方を根本から転換させる必要があり、大変な側面もあります。しかし見方を変えればこれは全ての職種にいずれ訪れる未来です。その変化を誰よりも先に体験し、乗りこなせるようになることは非常に大きなメリットだと考えています。

ーーその市場変化に対し、ファインディとしてはどのような戦略で対応しているのですか?
私たち自身が誰よりも変化に対応すべく、試行錯誤を続けています。たとえば企業の求人情報に「AIをどれだけ活用しているか」という項目を追加したり「Findy AI Career」のようなAIに特化したキャリア支援サービスを実験的に立ち上げています。この市場変化はあらゆる企業にとってこれまでの競合優位性が削り取られる瞬間でもあり、だからこそ挑戦の機会だと捉えています。
ーーSaaS事業「Findy Team+」の「カスタマイズモデルへの転換」という戦略について、詳しく教えてください。
マイクロソフトのCEOが「SaaS is Dead」と語ったように、本当の意味でスケールしている企業はAWSやSAPのように画一的なサービスではなくAPIを軸としたカスタマイズ可能なモデルを提供しています。私たちも同様に開発組織のパフォーマンス可視化というコアな価値を、SaaS画面だけでなくチャットUIやAPI経由でも提供できる体制に転換しています。生成AIの登場で、こうした大規模な基盤モデルをスタートアップでも開発できるようになったいまこそが、その好機だと考えています。
ーーグローバル展開について、インドでの再挑戦の経緯と今後の展望をお聞かせください。
実は一度、インドで人材紹介事業に挑戦し、日本と全く異なる手数料体系から撤退した苦い経験があります。しかしその経験から現地の開発組織が抱える課題を深く理解することができました。現在は「Findy Team+」でグローバルに再挑戦し、グローバルに開発拠点を持つ日本企業への導入も進んでいます。シリーズDで調達した資金も、まずはプロダクトを世界基準に引き上げるために投資しました。この領域は市場が非常に盛り上がっており、今後はインドを足がかりに、東南アジア、そしてヨーロッパへの展開も構想しています。
変化を乗りこなす、しなやかな組織

ーー競合との究極の差別化要因は「カルチャーとオペレーション」とのことですが、なぜそうお考えなのでしょうか?
プロダクトの機能は時間とともに模倣される可能性があります。しかし、その組織に根付いた独自のカルチャーと、そのカルチャーを基盤として日々磨き上げられる卓越したオペレーションは決して真似することができません。これこそが持続的な競争優位性の源泉になると考えており、だからこそ組織とカルチャーへの投資を最重要視しています。
ーー350名規模に拡大する中で、ファインディのバリューをどのように浸透させていますか?
専門のカルチャー推進チームを設置し、全社で取り組んでいます。行動指針として「前向き」「誠実」「チームワーク」「スピード」「No.1」という5つのバリューを掲げ、これを軸に採用や評価、表彰を行っています。
またバリューのアップデートの際には、経営陣のたたき台を元に全社員からフィードバックを募るなど、全員でカルチャーを創っていくプロセスを大切にしています。
ーー5つのバリューの中でも特にいま、重視されているのは何ですか?
どれも重視しているのですが、あえて絞るなら「スピード」でしょうか。生成AIの登場で、ビジネス環境の変化はますます加速しています。このスピードに対応できるかどうかが、企業の存続、ひいては社員一人ひとりの未来を決めると考えているからです。
ペーパーワークは合理化され、本当に価値を生む仕事に集中しなければ生き残れない時代が来ます。ファインディに来てくれたメンバーには、その変化の最前線で成長し、生き抜く力を身につけてほしいのです。

ーー成長企業のマネジメントにおける「優しさと厳しさ」のバランスについて、どのようにお考えですか?
新しく入社したメンバーから『心理的安全性が高く、働きやすい』という声をいただくことがあります。私たちはその信頼関係を土台に、メンバーひとり一人の成長とキャリアに本気で向き合うことを大切にしています。
インフレの時代に会社の生産性を高め、社員へ還元していくためには、チーム全体でより高い目標を達成することが不可欠です。そのため私たちは互いの成長のために率直なフィードバックを奨励し、個人の成長と事業の成果がしっかりと連動する環境づくりを進めています。これが、私たちがいま目指しているプロフェッショナルな組織の姿です。
ーーご自身を「大規模オペレーションが得意ではない」と分析されていますが、どのように組織を率いているのですか?
積極的に権限移譲を進めています。既存の主力事業は信頼するメンバーに任せ、私自身は新規事業やトップセールスに集中するようになりました。最近では私以外のメンバーからも新規事業が生まれるようになり、組織としての成長を実感しています。自分の不得手を認識し、得意なメンバーに任せる。それが組織全体のパフォーマンスを最大化すると考えています。
未来の仲間たちへ

ーーFindyが今、求めているのはどのような人物像でしょうか?
大きく二つのタイプの人材を求めています。一つは事業を非連続に成長させていく「攻め」の役割を担う人。もう一つは日々のオペレーションを実直に回し、私たちのカルチャーを体現してくれる「守り」の役割を担う人です。新しい事業が立ち上がるのは、既存事業を支えてくれているメンバーがいるからこそ。その両方をリスペクトし、共に成長していける方にぜひ仲間になっていただきたいです。
ーーエンジニアに求められる要素も大きく変わっているのでは?
繰り返すようですが生成AI革命は間違いなくエンジニアドリブンの変化です。エンジニアの生産性は飛躍的に向上し、プロダクトを社会実装するスピードは格段に上がっています。技術を理解し、それをどう事業に活かすかを考えられる人材がビジネスの中心になる時代が来たということです。
ーーファインディで働くことで得られる、キャリアにおける最大の価値は何だとお考えですか?
歴史的な変化の最前線にいる、という経験です。私たちはいま、この最もエキサイティングなマーケットのど真ん中にいます。社内ではAIツールの利用は無制限ですし、MVP受賞者には海外のテックカンファレンスに参加する機会も提供しています。この環境で成果を出すことができれば、大げさではなく、これからの数十年を生き抜くための市場価値の高いスキルが身につくと確信しています。「最も変化しているマーケットへようこそ」と、自信を持ってお伝えしたいです。

ーー採用パートナーであるProfessional Studioについて、どのような印象をお持ちですか。
私たちの組織を次のステージへと導いてくれるような、まさに「ゲームチェンジャー」となりうる人材との出会いを期待しています。事業を成長させるためには、その時々のフェーズで必要となる専門性や経験を持ったプロフェッショナルな人材の力が不可欠です。そうした方々との出会いを創出してくれる重要なパートナーだと考えています。
ーー実際にProfessional Studio経由で採用された方が、事業に与えたインパクトについて教えてください。
特に印象的なのは現在セキュリティ責任者を務めるメンバーの採用です。私自身、前職での経験からセキュリティ体制の強化は常に重要な経営課題でした。ご紹介いただいた方は事業成長とセキュリティ担保という相反しがちな命題のバランスを見事に取ってくれ、彼の入社後、ファインディのセキュリティレベルは格段に向上しました。これは将来のIPOを見据える上でも極めて重要な一歩であり、事業のステージを確実に一つ引き上げてくれた採用でした。
Professional Studioにはこれからも事業成長、組織成長のエンジンとなるような人材の採用に伴走してくださることを期待します。
三菱重工業で日本の「ものづくり」の真髄に触れ、コンサルティングファームでの挫折を味わい、スタートアップの最前線で事業創造のダイナミズムを体感した。山田代表のキャリアのすべてがファインディの「つくる人がもっとかがやけば、世界はきっと豊かになる」という理念に繋がっている。その言葉の端々からは、エンジニアという存在への深い敬意と、彼らの力を解放することで社会をより良くしたいという、純粋で力強い想いが伝わってきた。生成AIという大きな変化の波を乗りこなし、グローバルへと舵を切るファインディの挑戦はまだはじまったばかりだ。山田代表と彼のもとに集う仲間たちが描く未来に期待せずにはいられない。

最後まで読んで頂きありがとうございました。
『Startup Frontier』を運営するProfessional Studioは、スタートアップに特化したキャリア支援を行っています。エージェントはスタートアップ業界経験者のみ。キャリアや転職に関する相談をご希望される方は、以下よりお気軽にお問い合わせください。
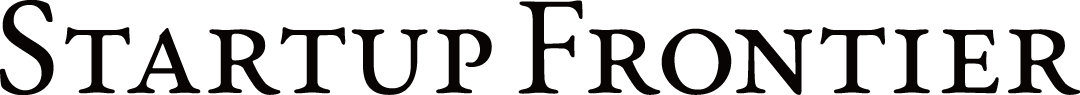

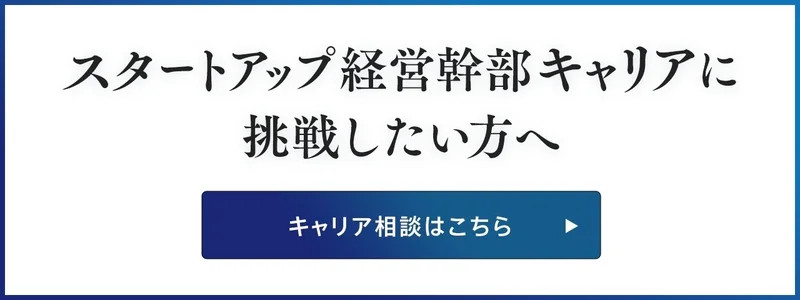 ≫無料相談はこちらから
≫無料相談はこちらから





